ITアーキテクトのひとりごと
第42回 「3.11東日本大震災が加速するクラウド」
今年の最大の話題は「3.11東日本大震災」だ。個人的には2回目の大地震だが、3回目が近々あるかもしれないので、備えを再点検しておく。個人的にできること、町内会でできること、自治体でできること、国でできること、たくさんやるべき事があるだろうが、それらが明確でなかったことが露見した。個人的には「諦めるべきところは諦める」というのが肝心だ。
ディザスタなんて起こって欲しくないことだから、考えたくない、というのは間違いであることが今さらながら再認識されたとは思うが、自分の利害に関連することでも、考えたくない派としっかりと考えていた派がいたようだ。考えたくない派もどこまで改心して考えるかは不明だが、たぶん、ほとんどの人は(今はまだ)気にはとめているが、忘れつつあるというところだ。
企業のITシステムのディザスタ対策も、いろいろと考えてはみるが、自分の利益との関連性、公共的な利益との関連性の認識が十分でないと方向性が定まらない。結局は考えたけどそのまま手つかず、なんていう事例はゴロゴロしている。考えてくれと頼まれるSIerはほとんどの場合ただ働きになるので何とかして欲しい。お客様の本気度が見えないと安直な提案になりがちだ。ディザスタリカバリを実現させるキーポイントは諦め方にある。
原子力発電所の事故も究極の割り切りは、このような設備を止めてしまうことになるのかも知れないが、それ以前にインパクト分析がダメダメだったのはビックリするのを通り越して情けない。
このような大規模設備でなくても、インパクト分析の悪い結果を関係者に伝える時は勇気が必要だ。自分が悪くなくても。
サプライチェーンの問題も認識されたが、事業会社の利益にも関わる話に国が介入するわけにもいかないので、どのようにコンセンサスを作ったらよいのだろうか。鉄は熱いうちに打て。問題意識があるうちにコンセンサス作りのための協議体を作ったとしても、現代はグローバルな競争社会なので、自分だけで考えておけば良いわけではないところが問題を複雑にしている。
タイの洪水も、世界的にサプライチェーンの問題を再認識させたが、局所的な最適解を求めている限り、結局は逃げるところは無さそうだ。この問題に対する多くの対応策が各社から発表されているが、ノウハウの拡散につながる選択もありつらい。通信、運輸の発達で、昔は広いと思っていた世界が意外に狭い。狭くなってしまった地球を逃げ出すこともできない圧迫感だけが残る。
さて、この大震災をきっかけに、これまでフワフワしていたクラウドが本当に地に足を付けることになりそうだ。正しいかどうかは別にして、クラウド = データセンター という認識も非常に強くなっているが、期待値が大きくなる分だけブレも大きくなるので注意しないといけない。
「クラウドでやりたい」。。。こんなことを言う人が増えているが、これってデータセンターを使いたいという単純な意味で理解していいのか。データセンターも被災する可能性があるので、アプリ業務をサービス化してロケーションフリーにしたいという理想型で語っていると大変なことになる。そういえば「SOA」というバズワードもあった。ロケーションフリーなサービス化されたアプリ業務なんてSOAの見本みたいな話だ。出来る、とは思うが実践しているのは数少ないサービス事業者だけだ。
こんなことができるのは、自前のITインフラ、ネットワーク、運用能力、そして十分な資本を持つサービス事業者だけだ。もちろん、サービスそのものの出来不出来が重要だが、クラウドのプレイヤーになるための門は急速に狭くなっており、スタープレイヤーになるための門は更に狭い。
クラウドのプレイヤーになるのか、ならないのか。クラウドがカバーするサービス範囲が急速に拡大しているので、どちらにしても自分のプレースタイルの再考が迫られている。
株式会社エクサ 恋塚 正隆



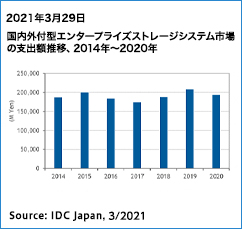
 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム JEITA連載寄稿
JEITA連載寄稿 「Storage Magazine」
「Storage Magazine」
