【新連載】ITアーキテクトのひとりごと
第28回 「ファイルサーバの『見える化』 ~「見える化」への遠い道~」
ファイルサーバによって、情報共有のスピードは格段に上がった。そもそも、会社の仕事から生じた成果物であるドキュメントは、個人のPCから公の場であるファイルサーバに保存すべきものだ。そうはいっても、どこに、どんな順番で保存するべきか、古い版をどこにどのようにアーカイブすべきかは、いつも悩む。無くなるよりいいや、とばかりに適当に整理フォルダに置いておくと置いたことすら忘れてしまうくらいだから後からサルベージするのは大仕事だ。
設計図や仕様書のように文書体系が決まっているものは、ほとんど悩むことは無い。時間をかけて形式が完成しているからだ。それでも、「これはどうしたらいいの」という問題は常に生じるので、文書のメンテナンスは重要な仕事になる。
設計図や仕様書は一定のルールに基づいて構造化された文書だが、大多数の文書は構造化されていない。文書を有効に利用するには、目的にあわせて非構造化文書から構造化された文書を作り出す作業が必要になる。この作業にオフィスワークのかなりの時間が消費される。
ファイルサーバ統合は、構造化された文書の保管先としての有効性はあるかも知れないが、非構造化文書の保存先としての有効性は、集中バックアップが簡単になる、ストレージシステムの使用効率が上がる、くらいしか無いかも知れない。まあ、それでもコスト的には相当な効果を出すことが予想されるので、やらないよりやった方が良いに決まっている。しかし、予算を引き出す名目としてはいいが、オフィスワーカーの生産性はどの程度上がるのだろうか。
ファイルサーバ統合によって、暗黙知が形式知になるような錯覚を覚えるようなことがあるが、そんなことは無い。実現できたのは、改めて自分の持っている文書の量が理解できたことと、その文書を効果的に保管、管理できるようになる第1段階に達したことぐらいだ。本当の『見える化』にはいくつもの大仕事が待ちかまえている。
この第1段階までがファイルサーバ統合の役目なのかもしれない。さて、次の第2段階、第3段階へと進むための方法論が見えない。第1段階だけでも簡単に一定の効果が出ているので、次の段階に挑戦するような"無謀"なことは心の中にそっとしまっておくのがベストかも知れない。ナレッジマネジメントがその答えを持っているのかも知れないが、正直に言って、効果的なナレッジマネジメントってどんなことなのか、サッパリわからない。何かとてつもなく大変そうなので触りたくもないし、面倒でお金がかかった上に効果も定かでないので、うかつに何かやると後ろ指を指されそうだ。
社内SNSや社内ブログ、グループウェア、チャットを組み合わせれば少しは上手く行くのかも知れないが、そもそもナレッジマネジメントなんて、"ナレッジ"を管理するなんて言った時点で大変なことを言っているとしか思えない。自分の持つナレッジが何なのか識別できていないことが多いだけでなく、自分が変化して、世の中が変化しているとナレッジを見る視点、スコープが変わっていくので、そのナレッジを管理しているだけで精も根も尽き果てそうだ。
ファイルサーバ統合でわかるのは、結局、このファイルサーバにあるデータが自分の持っている全てのデータだ、ということを再認識できたことだ。活用できるか? それはファイルサーバ統合とは別次元の問題であることを再認識することにもなる。自分の持っているナレッジが全て文書化されているとして、ファイルサーバ統合は、その文書がそこに入っていることしか保証していないのだ。
株式会社エクサ 恋塚 正隆



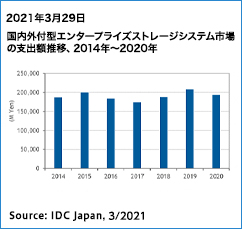
 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム JEITA連載寄稿
JEITA連載寄稿 「Storage Magazine」
「Storage Magazine」
