HOME > ストレージ・ネットワーキング技術部会 > ファイバチャネルFAQ(よく出る質問)
-
・ファイバチャネル技術を採用する製品を提供するシステムベンダーについて教えて下さい。
主要システムベンダーのほとんどが、自社製品にファイバチャネル技術を統合しています。 -
・ファイバチャネルの啓蒙活動を行う団体について教えて下さい。また連絡をとる方法についても教えて下さい。
ファイバチャネル技術の啓蒙活動を行う団体には、FCIA(Fibre Channel Indutry Association) がありますが、SNIA (Storage Networking Insutry Association) もファイバチャネル技術の啓蒙活動を行っています。
日本においては、以下にご連絡ください。
JDSF ファイバチャネル技術部会
E-mail : info2@jdsf.or.jp
SNIA-J
E-mail : office@snia-j.org -
・ファイバチャネルの相互運用性の確立の為の活動を行う、テストラボ及びインテグレーションラボについて教えて下さい。
Lawrence Livermore Laboratory及びNew Hampshire大学が、ファイバチャネルのインターオペラビリティラボを運営しています。商目的と科学的興味の統合としてはよくあることですが、LLNL(Lawrence Livermore National Laboratory)は、企業からの資金援助を受けて、テスト環境を整備してきました。LLNLは、ファイバチャネルの相互接続性及び相互運用性のテストの受け皿となっています。ファイバチャネル製品の開発会社は、両者の合意のもとに、サービス及びハードウェアを無償提供して、相互接続性及び相互運用性の事業を推進しています。
New Hampshire大学は、ファイバチャネルネットワーキングラボを運営しており、同ラボも同様に機能しています。New Hampshire大学は、協調的に相互運用性に関するプログラムを推進するファイバチャネル協議会のメンバーである、FCC(Fibre Channel Consortium)に対して、オンサイトのサポート及びテクニカルサポートを提供しています。
-
・各社ベンダーのファイバチャネル製品の互換性について教えて下さい。
ネットワーキング技術全般に言えることですが、1個のベンダーが他社製品との互換性をもたない製品を開発することはいたって簡単なことです。開発当初の266Mbpsのファイバチャネルスイッチにおいては、各社ベンダーが互換性をもたない製品を提供するケースもありました。しかし、今日の1Gbpsをサポートするファイバチャネル製品は、相互接続性・相互運用性が提唱されるなかで、オープンな環境で開発されてきました。ファイバチャネルはオープンスタンダードな技術であり、標準に準拠するファイバチャネル製品は、相互接続性を提供します。主要システムベンダーのほとんどが、ディスク及びディスクアレイにおいて、ストレイジのネットワークにファイバチャネルを統合する技術の開発を進めています。将来的な、1GbitのFLポートの仕様の標準化,1Gbitのアービトレイテッドループトポロジとスイッチドトポロジ間のリンクの標準化の実現は、ファイバチャネル製品の相互接続性に大きな前進をもたらすことでしょう。各社ベンダーが特長的に存続する限り、標準に準拠する相互接続可能な製品を提供することで、大きな恩恵を受けることでしょう。
異なる伝送速度で動作するFC-ALもしくはクラス1製品を相互に接続する場合には、ルータが必要です。1個のPCもしくはサーバの複数のI/Oスロットに266Mbpsのアダプタカードと、1Gbpsのアダプタカードを搭載することにより、266スイッチをギガビットのループに接続することができます。
-
・ファイバチャネルの開発と標準化の歴史について教えて下さい。
ファイバチャネルは、ANSI X3T11委員会での標準化が進められています。1996年、Hewlett Packard, IBM RISC及びSun Microsystemsのワークステーション会社3社は、FCSI(Fibre Channel Systems Initiative)を設立しました。3社の興味は、既存のファイバチャネルスタンダードを踏まえた上での、SCSI及びIPの相互運用性の規定にありました。FCSIは、これを実行する為に、ファイバチャネル技術の一連のプロファイルを開発したのです。プロファイルの開発完了後、FCSIは解散し、プロファイル開発及びサポートは、FCA(Fibre Channel ssociation)に引き継がれました。現在、FCA及びFCAのワーキンググループのFCLC(Fibre Channel Loop Community)は、FCAL技術の採用を推進するファイバチャネルインダストリにおける、マーケティング活動の中枢として機能しています。
-
・ファイバチャネルの標準化は、ANSI標準化委員会を中心に進められているのですか。
ファイバチャネル標準化の主要委員会は、ASC(Accreduted Standars Commitee)X3T11です。X3T11の傘下で、多数のワーキンググループが活動しており、各グループごとに標準の特定部分の規定を進めています。委員会の活動については、委員会委員長までお問い合わせ下さい。現在の委員会委員長は、DPTのRoger Cummings氏です。
-
・ファイバチャネルの仕様についての資料を入手したいのですが、入手方法を教えて下さい。
認定された標準及び、ドラフトのドキュメントは、インターネット経由で入手することができます。FCLC,FCAのホームページをご参照下さい。また、Global Engineering社が、ワーキングドキュメント及びドラフトスタンダードのドキュメントを有償で提供しています 。
Global Engineering社:
電話番号:800-854-7179 / 300-792-2181
FAX番号:303-792-2192
住所:15 Inverness Way East Englewood, CO80112-5704 ・標準の名称について教えて下さい。
「FIBRE CHANNEL STANDARDS」です。
ANSIX3T11ファイバチャネル標準及び、ドラフトスタンダード。
- FC Physical(FC-PH)
- FC REference Card
- FC-PH-2
- FC-PH-3
- FC Arbitrated Loop(FC-AL)
- FC Protocol for SCSI(FCP)
- FC Protocol for 802.2LE(FC-LE)
- FC Protocol for HIPPI(FC-FP)
- FC Protocol for SBCON
- FC Generic Service(FC-GS)
プロファイル
- FCSI Profile
- FCSI Profile Structure, FCSI-001
- FCSI Common FC-PH Feature Sets, FCSI-101
- FCSI SCSI Profile, FCSI-201
- FCSI IP Profile, FCSI-202
- Gigabit Link Module Specification, FCSI-301
- Loop Profiles
- Private Loop Direct Attach document
- Public Loop Profile, FC-PLP
その他のファイバチャネルの仕様及びドキュメント
- N-Port to F Port Interoperability
- 10-Bit Interface Specification
- FC MIB
- Fibre Channel Optical Converter Proposed Specification
-
・ファイバチャネルの標準化についての資料を入手したいのですが、入手方法を教えて下さい。
認定された標準及び、ドラフトのドキュメントは、インターネット経由で入手することができます。FCLC,FCA,Cernのホームページをご参照下さい。また、Global Engineering社が、ワーキングドキュメント及びドラフトスタンダードのドキュメントを有償で提供しています。
Global Engineering社:
電話番号:800-854-7179 / 300-792-2181
FAX番号:303-792-2192
住所:15 Inverness Way East Englewood, CO80112-5704 -
・上記以外に推奨できるファイバチャネルの資料はありますか。
海外では多くのファイバチャネル、ストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)の著書があります。日本語の著書としては、以下をお勧めいたします。
「ファイバチャネル技術解説書 II」
JDSF ファイバチャネル技術部会監修・執筆
論創社 ISBM4-8460-0542-9
「SAN & NAS ストレージネットワーク管理」
JDSF理事監訳
オライリー・ジャパン
ISBN4-87311-099-8

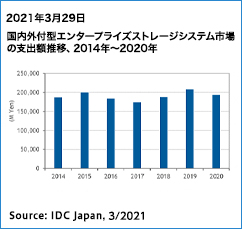
 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム 恋塚正隆の連載コラム
恋塚正隆の連載コラム JEITA連載寄稿
JEITA連載寄稿 「Storage Magazine」
「Storage Magazine」
